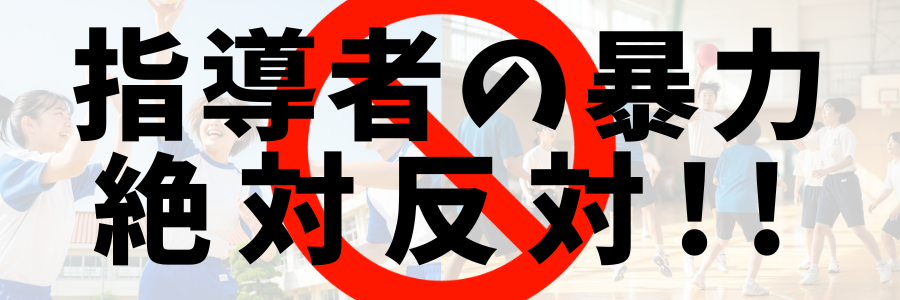毎年1月に開催される「全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)」に向けて、全国各地で予選開始の時期を迎えている。
その中で神奈川県は、2校が本戦へ出場できるとはいえ、予選出場校が多い上に名門・強豪・新興勢力が入り交じる激戦区といえる。
長らく1強+他で代表校が決まっていた地区だが、近年は大きく様変わりしている。勢力図を変えた要因の一つは、全国有数の「知の名門」で知られる慶應義塾高校の台頭だ。
同校は約10年前まで県内でほとんど上位に進出することがなかった。しかし、選手時代に春高制覇するなど高いレベルでプレーをしてきた渡辺大地先生が着任してから、時代に合わせた指導によってチーム強化が急速に進んだ。
不定期連載「指導者たちの心得」第7回は、「選手の自立」を掲げて監督就任2年目でチームを春高へと導き、以降全国大会の常連となった同校・渡辺先生の指導哲学を紹介。前編は、渡辺先生の背景、赴任~春高初出場までのエピソードをお送りする。
(11月15日追記:神奈川県第1代表として2年連続6度目の春高出場決定)
「優しいお兄さんたち」と日体大への憧れ

小さいころからスポーツが好きだった渡辺先生は、時間を見つけては友達を誘って野球や卓球、バドミントンなどを楽しんでいた。父親がバレーボールの指導者ということもあって、土日は家族で練習試合に〝同行〟していたという。
「当時、父のチームとよく練習試合をしていたのが、八木義光監督率いるサレジオ中学(東京都)※で、中学生のお兄さんたちが小学生だった自分にすごく優しく接してくれたんです。小学4年生の時、本格的にバレーを始めたんですが、漠然とお兄さんたちと同じ所でバレーがやりたいと思うようになりました」
※長年同校で教員を務めた八木監督の下、関東大会、全国大会優勝などの実績を誇る中学バレーの名門校。
地元のバレーチームでのプレーを経て、渡辺先生の思い描いた通りにサレジオ中学へ進学する。当時のサレジオ中学は好メンバーぞろいで、全国大会を狙える実力があった。渡辺先生は中学2年時に全国優勝を経験すると、3年時には全日本中学選抜の海外遠征メンバーにも選出された。
代表レベルの選手ともなれば、全国の高校から声がかかる。いろいろな高校と話をして進学先を検討する中、渡辺先生には重要なカギがあった。
「父も八木監督も日本体育大学OBで、自分もスポーツが好き。大学で勉強すれば、体育の教諭になれる。必然的に、日体大への憧れが強くなっていきましたね」
強豪高校と大学の間には、俗にいう〝パイプ〟がある。日体大とのパイプがある高校も進学先の候補にはあったが、「全国優勝」への思いが勝った。
そして渡辺先生が選んだのが、前年(2007年)の第38回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会(春高バレー)を制した東亜学園だった。多くのバレー仲間が進学予定だったこともあり、優勝の可能性は十分あると思っていた。そこで自分が結果を残せば、日体大への道も開けるとも考えていた。
東亜学園進学後は、第39回大会(2008年)で1年生ながら優勝メンバーに名を連ね、チームの連覇達成に貢献。翌年は主将としてチームを引っ張り、ベスト4へと導いた。
高校での実績をひっさげ、渡辺先生は憧れであり、目標だった日体大へ進む。ここまですべての年代で主将を務めてきたが、大学でも同じだった。
「精神的に未熟だった中学・高校時代、自分のやり方を押しつけるつもりはなかったですが、負けず嫌いが強く出てしまって、うまくチームを引っ張れなかったことがあったかもしれません。
だから、大学ではその点を意識し、仲間の意見を聞きながら、チームをまとめていく手法を取ることにしました。日体大で経験し、学んだことが、自分の人間性の確立に大きな影響を及ぼしたのは間違いないですね」
4年間バレーと向き合い、教員免許を取得した後、2014年に慶應の教諭として勤務を始める。
「やらされた」現役時代とのギャップ、「言葉」の重みを実感
中・高・大といずれもバレーの名門校で全国優勝も経験し、常にチームを引っ張る存在だった渡辺先生。赴任した慶應はスポーツも盛んだが、勉強に力を入れる生徒が多い。バレー部の目標もそれほど高くない。
現役時代とは異なる状況の中、渡辺先生が受けてきた指導は通用せず、理想の監督像も全く見えない状況だった。
「選手のころは監督に言われたことだけを当たり前にこなしていたので、考えることをあまりしてこなかったように思います。そのため、『自分はこんなにも人に伝える力やコミュニケーション能力が不足していたのか』と自覚しました。ここは、社会に出てから苦労した点ですね。
当初は選手たちに〝やらせる〟意識が強く、高圧的な物言いをしたり、説明をしないで練習をしたりしていましたが、選手たちから強い反発がありました。
当然ですよね。私の当たり前は、選手たちにとっての当たり前ではないんですから。『なぜ練習をするのか』の理由をきちんとつけてあげないと理解できない。自分の経験とのギャップがありましたし、難しかったですね」
「言葉で伝える」ことの重要性に気づき、渡辺先生は進むべき指導の方向性を徐々に見出していく。
バリバリの現役時代を過ごした渡辺先生だが、監督就任以降、選手たちに手本を見せることはほとんどなく、全くコートに入らない日もある。
「若い時は動けるので、選手の手本になって教えることができますが、それができなくなったら、言葉で説明する以外に方法がなくなるんです。
だったら、最初(監督就任時)から言葉で説明して、選手たちに理解してもらう形でいこうと決めました。必要なことを伝え、その後は選手主導でやって行く。
そうすれば、極端な話、自分がいなくてもチームは作られていきます。大きく指導方針を変える必要もないので、合理的だと思います」
一見、放任とも思える指導法だが、選手たちの将来を考えてのものでもある。
「選手たちが能動的なら、自然といろいろなことを考えるようになります。やらされる指導を受けたまま社会に出た時、私と同じ苦労をしてもらいたくない。その思いも強かったですね」
指導者としてスタートしたばかりの頃は、未熟な点が多く壁にぶつかったものの、少しずつ改善していった。
〝春高1期生〟主将との衝突、見えた指導の方向性

選手たちに言葉で説明し、理解してもらい、自ら考える―渡辺先生は「選手の自立心を育む」を第一に慶應の強化を進めていく。
決して強豪とはいえない慶應の監督に就任したが、赴任してから1年間コーチとして見てきた選手たちには光るモノを感じていた。
「能力の高い子たちが集まっていたので、『春高、絶対行けるよ!』『能力はあるよ』と言い続けていましたし、監督になった最初のミーティングでも強調しました。
3年生は当時、インターハイ(IH)予選が終わると引退し、2年生を主力としたチームで春高予選に臨んでいました。だから、3年生たちには『夏で引退したら、春高へ行ける可能性は0。自分たちで続けるかどうかを話し合って』と伝えました。
結局、彼らは引退せずに残ってくれて、県ベスト4と全国に届く所まで導いてくれました。彼らのおかげで、今の慶應があると思っています」
春高まであと一歩の所まで来たチームを引き継いで主将を務めたのが、渡辺先生と同じサレジオ中学出身で、全国優勝を経験した選手だった。結果として、このチームが創部68年目にして初めて春高出場を果たすことになる。渡辺先生が監督に就任してから2年目のことだった。
彼はもともと勉強のために慶應へ進学したが、顔見知りの渡辺先生と思わぬ再会をしたことで、バレー・春高への思いを強くしていった。渡辺先生も「何とか春高へ連れて行ってあげたい」といった思いを日に日に募らせていった。
思いが強い者同士の間では、時に不協和音が生じる。お互い本気ゆえに、監督と主将は〝衝突〟した。
主将がある日、思うようにプレーができず、不貞腐れた態度を取っていると、渡辺先生が指摘する。主将は、ここぞとばかりに「先生の練習の意図がわからない」など言葉を浴びせ、次第に口論へと発展する。渡辺先生は「じゃぁ、自分で考えろ」と突き放し、その後チームと距離を取った。
「まるで、子どものケンカですよね(笑)。当時は私も若かったし、負けん気が強いので思わず(笑)。でも、彼の気持ちも理解できました。私の高校時代と重なっていましたし、同じことをしていたと思いますよ(笑)。
主将はメチャクチャ能力が高くて、自分で考えられる子。あとで謝りに来ましたが、『このまま俺がやるのではなく、自分たちで考えなさい』と伝えました。
それから彼はチームをまとめ、他の選手たちと一緒に勝つための道筋や戦略を練っていきました。この時から、本気になっている選手たちを支え、必要な時に助言するといった私の基本的なスタイルが確立されました」
この出来事以降、(現チームでも)渡辺先生と選手の間ではしばしば〝議論〟が展開されるという。指導者と選手、「はい」と「いいえ」でしか成り立たない関係性は、慶應にはない。
「屁理屈になることは大事なことだと思っています。相手の虚をつくことにもつながりますしね。あと、『先生が言ったことを疑問に思いなさい』とも言っています。
『え、先生こういったけど、こうじゃないの?』『いや、先生はこう思うよ』『でも・・・』といったやりとりが、結果的にいい方向へ行く。まさに議論ですよね。
『自分はこう思います』と意思を伝える力が身につきますし、議論を深めていくと、意図を理解してくれたり、考えが同じになってきたりするので、自然とその頻度は減っていきます。
『なぜ』を放置したままだと、100%の力で練習できないので、それを解決するために議論をする。高圧的に『やりなさい』とは決して言いません」
監督に就任して早々と結果を出した渡辺先生だが、この成功体験はジレンマを生むことにもなった。
「結果が出てしまったというのが正直なところです。次の代でも同じことができるのか、練習を厳しくすればいいのかと、その後いろいろな課題が出てきました。
『結局、何が正解なんだ?』と4年ほど考え続けた結果、ようやく自身の指導理論が明確になりました。今はどの代でも同じやり方をすれば負けない自信がありますね」
渡辺先生の言葉通り、慶應はこれまでに春高5回出場、IH4回出場と、ここ10年で県内をリードする存在になった。
「今年の目標は日本一。選手たちが決め、私はそのためのあらゆるサポートをしています。神奈川県は強豪校の多い地区ですが、慶應らしいやり方で、他のチームにはプレッシャーをかけ続けていきたいですね」
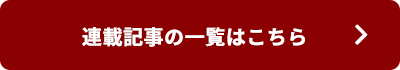

慶應義塾高等学校
1868年、福沢諭吉が創始した「蘭学塾」を「慶應義塾」と命名。1949年、慶應第一、第二高等学校を統合し、日吉へ移転。現校名となる。
第102・103代内閣総理大臣・石破茂氏、トヨタ自動車代表取締役会長・豊田章男氏、俳優・石原裕次郎氏ら、あらゆる分野に人材を輩出する。
2023年夏の甲子園で野球部が107年ぶりの優勝を果たすなど、近年はスポーツでの活躍も目覚ましい。