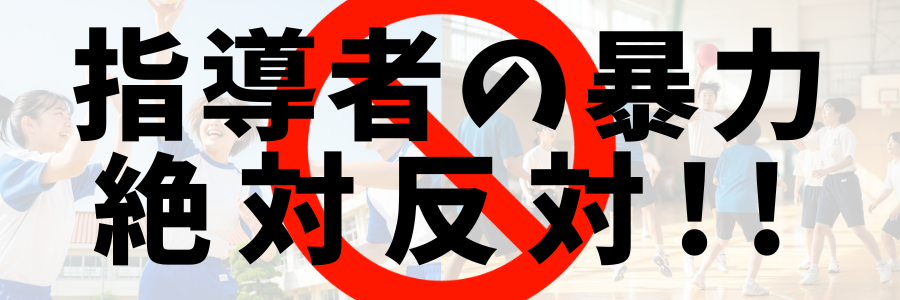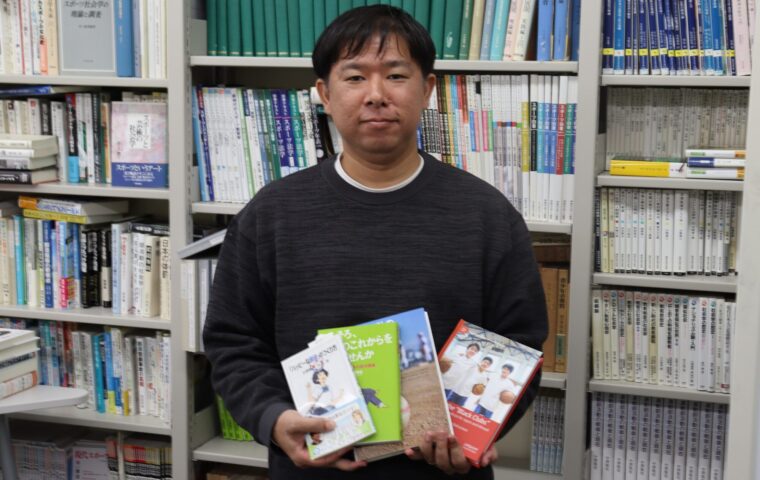運動前のウォーミングアップは必要なのか?

ジョギングをして、腕や脚を伸ばすストレッチをして…何となく習慣として取り入れていても、心のどこかで「やらなくても大丈夫なのでは?」と思っている方も多いでしょう。
ところが近年、スポーツ医科学の研究は、準備運動(ウォーミングアップ)が「ただの習慣」ではなく、身体と脳を最高の状態へ導く「科学的なスイッチ」であることが次々と明らかになっています。
ケガの予防はもちろん、パフォーマンス向上、さらには「頭の働き」や「気分の切り替え」にまで影響を与えます。ウォーミングアップは、私たちの身体と心をトータルに整えてくれる「万能ツール」なのです。
サッカー日本代表やNBA選手のウォーミングアップルーチンを見ると、わずかな時間で集中力と瞬発力を高めるための工夫が満載です。
ウォーミングアップは競技ごとに最適なものがありますが、今回から3回にわたって、日ごろスポーツを楽しんでいるみなさんに向けた「ウォーミングアップの基礎」をお送りしていきます。
ウォーミングアップ②RAMPプロトコル»|ウォーミングアップ③実践»
ウォーミングアップは「身体のスイッチ」
「なぜウォーミングアップをするのか?」。この意味を身近なことと紐づければ納得いただけると思います。
冬の朝、車のエンジンがかかりくいといった経験をしたことがあるのではないでしょうか? その時は暖機運転でエンジンオイルを温めてから、車を動かしますよね。車の準備が整わず、いきなり走らせてしまうとエンジンなどに負担がかかり、思わぬ故障をひき起こします。
人の身体も車と同じように、休んでいる状態(安静時)から急に全力で動けるようにはできていません。筋肉を温め、神経系を目覚めさせ、心拍数や呼吸を徐々に上げることで、身体は自然に「運動モード」に切り替わります。ウォーミングアップは、まさに「始動のための準備」であり、「身体のスイッチ」なのです。
ウォーミングアップをしっかりやることで、運動パフォーマンスが最大化されるだけでなく、ケガ予防や集中力向上にもつながっていきます。
ウォーミングアップの科学的効果
① 体温と筋肉の温度を上げる ~パフォーマンス向上のカギ~
ウォーミングアップの主要な目的は、「深部体温と筋肉の温度を上げること」です。
温まった筋肉は粘性抵抗が減り、筋収縮や神経伝達速度が向上します。その結果、動作がスムーズになり、反応時間や瞬発力が改善されます。実際、筋肉の温度がわずか1℃上昇するだけで、反応速度が約3〜4%速くなるという報告もあります。
スポーツ選手だけでなく、日常的に運動する人にとっても大きな違いを生む数字です。通勤前に軽く足踏みや腕回しをするだけで、身体の軽さや集中力の違いを感じられるはずです。
② 関節の動きをスムーズにする ~可動域の拡大と柔軟性の向上~
身体が温まると血流が増え、関節包内の滑液の粘性が低下し、関節可動域が広がります。関節周囲の軟部組織も柔らかくなり、運動中の動きが円滑になります。
③ ケガを予防する ~安全な運動のために~
冷えた筋肉や腱は硬く、急な伸張に弱いため、肉離れや靭帯損傷のリスクが高まります。
ウォーミングアップによる筋温上昇、関節可動域の拡大、神経筋系の活性化は、運動中のケガのリスクを大幅に低減させます。特に、動的なウォーミングアップは、関節の安定化や運動パターンの最適化にも効果的です。
さらに、心拍数や呼吸数が徐々に上がることで、心臓や肺への負担も和らぎます。中高年世代にとって、準備なしにいきなり運動を始めることは、心血管系のリスクを高める可能性があります。
④ パフォーマンスを高める ~最大限の力を引き出す~
ウォーミングアップはケガを防ぐだけでなく、実際に運動の質を高めることが分かっています。
特に、身体を動かすことで筋肉が一時的にパワーアップする現象「ポスト・アクティベーション・ポテンシエーション(Post-Activation Potentiation:PAP)」が起こり、これがスプリントの速さ、ジャンプの高さ、ボールを投げる距離、素早い方向転換など、さまざまな運動能力を高めることが多くの研究で証明されています。
運動に合わせたウォーミングアップを行うことで、実際の動きに必要な神経回路が活性化され、最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。
⑤ 心肺機能の準備 ~エンジンを温める~
ウォーミングアップは筋肉や関節だけでなく、心臓や肺の準備にも重要です。
軽い運動で心拍数と呼吸数を徐々に上げ、血液を促すことで、筋肉に効率よく酸素が運ばれます。その結果、乳酸の蓄積も遅くなるため、疲労を感じにくくなります。
例えば、5分間の軽い有酸素運動を行った後に本格的な運動を始めると、最大酸素摂取量(VO₂max)の立ち上がりがスムーズになり、パフォーマンスが長く維持できることが分かっています。
つまり、「いきなり全力」ではなく「段階的に負荷を上げる」ことで、身体は本来の力を発揮できます。
⑥ その他
・脳と筋肉の連携を活性化
運動神経が活性化されることで、反応時間が短くなり、素早く正確な動作が可能になります。トップアスリートが入念にアップを行うのは、筋力のためだけでなく「脳と身体の連携」を整えるためでもあるのです。
・心理的な効果
不安や緊張が和らぎ、集中力が高まることも知られています。実際にウォーミングアップをした選手は、不安を抱えたまま試合に臨んだ選手よりも安定したパフォーマンスを発揮するという研究もあります。
次回は、ウォーミングアップの流れや注意点をお伝えします。(前道 俊宏)
【引用文献】
・Wilson CJ et al.: The effect of muscle warm-up on voluntary and evoked force-time parameters: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. J Sport Health Sci (2025)
・Sople D et al.: Dynamic Warm-ups Play Pivotal Role in Athletic Performance and Injury Prevention., Arthrosc Sports Med Rehabil (2024)
・Sadigursky D et al.: The FIFA 11+ injury prevention program for soccer players: a systematic review., BMC Sports Sci Med Rehabil (2017)
・Silvers-Granelli H et al.: Efficacy of the FIFA 11+ Injury Prevention Program in the Collegiate Male Soccer Player., The American Journal of Sports Medicine. (2015)
・安田好文 : ウォーミングアップが運動時の生体機能に及ぼす影響について, デサントスポーツ科学 (1983)
【前道先生への質問を募集します!】
トレーニングや怪我予防など、読者の皆さんが持つ疑問に前道先生がお答えします。
五輪やトップスポーツ現場での経験を持つ有識者から直接アドバイスいただける機会は少ないので、ドシドシ質問をお寄せください。質問はこちらから。
※返信のために、お名前(ハンドルネームでも可)・連絡先(メールアドレス)が必要になります。
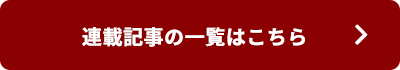

前道俊宏(早稲田大学スポーツ科学学術院講師、東洋大学ライフイノベーション研究所客員研究員)
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)、鍼灸あんまマッサージ指圧師。スポーツ医科学・臨床現場を架橋する研究を推進し、運動器障害の評価と予防、介入効果の可視化に関する研究に従事している。