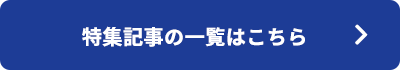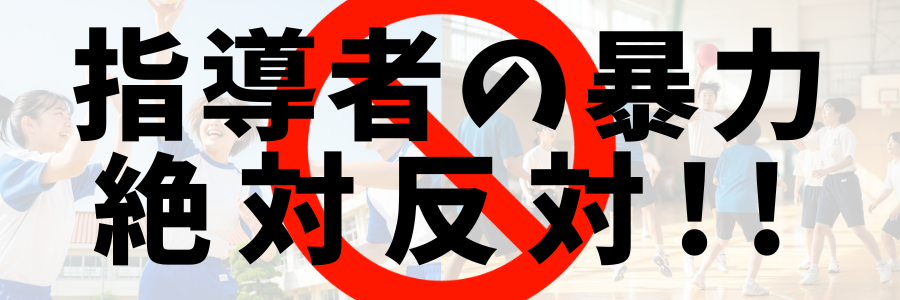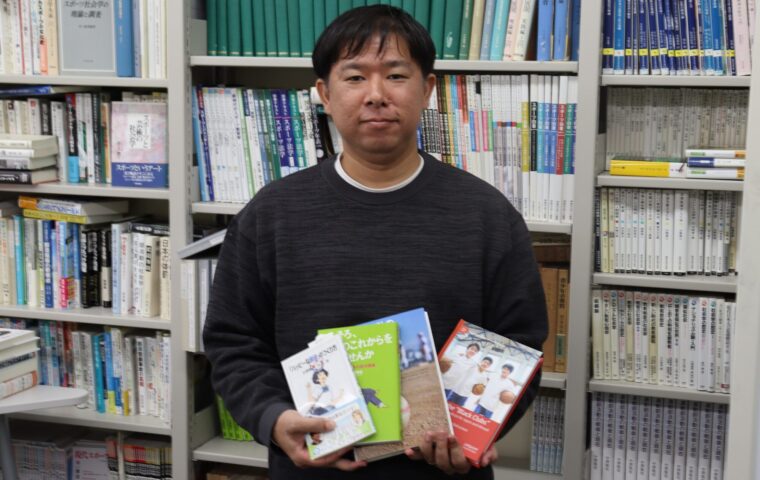前回に引き続き、子どもの偏食の話題をお送りします。
偏食にはさまざまな要因が考えられるため、無理に食べさせるのではなく 「食べてみようかな」と思えるきっかけをつくることが偏食克服につながります。今回は、子どもが苦手な食べ物を克服するための具体的なアプローチ方法をご紹介します。
成功体験をつくろう!

偏食を克服するためのアプローチ方法は、一人一人異なります。「成功体験」を感じる要因としては、「ひと口でも子どもが自分で口に運ぶことができた」「お皿を空っぽにできた」「食べたことで調理してくれた人が喜んでくれた」などがあります。
大人が環境を整えますが、大人に食べさせられるのではなく「子どもが自分で食べる」という自発的な行動が克服のカギとなります。
自分で食べる量が決められるようになったら、どのくらい食べられるのかを子どもに聞いてお皿に盛りつけ、その量を食べきることも自信につながります。
大人が口を挟みたくなりますが、そこはぐっとこらえ、野菜の小さなかけら1つからでも「食べられた」の体験を積み重ねてあげられるといいですね。
「食材」に触れる機会をつくろう

何度か目にしたり、触ったりする経験を重ねていくと、食材への興味・関心は高まります。また、大人が「この料理には何が入っているかな?」「これはどんなかたち?」など、料理や食材の話題を出して話をすることで、子どもも同じものに興味を持つようになります。
一緒の時間を過ごしながら、食材に触れる機会をつくっていきましょう。
①一緒に料理をする
子どもと一緒に料理を作るときには、「こぼす」「汚れる」「けがをする」などの心配が多く、一緒に作る大人のほうが疲れてしまうことのほうが多いかもしれません。
しかし、難しいことをする必要はありません。「野菜を洗う」「玉ねぎの皮をむく」、学童期であれば「調味料を計って混ぜ合わせる」など、大人の余裕があるときに、子どもと一緒にキッチンで食べ物に触れる時間をつくってみましょう。
②一緒に食材を買いに行く
キッチン以外にも、食材に触れる機会は多くあります。一緒にスーパーへ買い物に出かけるといろいろな食材を見ることができます。触ることはできなくても、「どれにしようかな?」など買い物をしながら一緒に話をするだけでもいいですね。
あえて苦手な野菜を一緒に買って持ち運ぶお手伝いをお願いすると、自分が家に持って帰ってきた野菜!という特別感が演出できます。
③野菜を育ててみる
日当たりの問題、土やプランターなど栽培するために準備するものはありますが、「野菜を育て、収穫して食べる」という経験は、子どもにとってとても貴重な体験です。「葉や茎が伸びてくる」「蕾ができて花が咲く」「小さな実が育つ」など、栽培の過程を見ることで、育てた野菜への愛着が沸き、収穫して食べる楽しみはひと際大きくなります。
特にラディッシュや枝豆、リーフレタスなどは育てやすく、プランターでも楽しめます。ぐんぐん伸びたり、葉の色が変わる様子が分かりやすく、子どもたちの観察にもピッタリ。収穫して食べる喜びも大きく感じられるはずです。
④食べたい料理をリクエストしてもらう
子どもに食べたい料理を聞いてみることも、食に関わる話題の一つです。いろいろな料理や食材がわかるようになってきたら、「今日は何が食べたい?」と声をかけてみましょう。希望した食事が用意されると「食べたい!」の気持ちも高まります。
いつもリクエストに応えることは難しいですが、「今日はリクエストの日」と決めるなど特別感のある日をつくってみるのもいいですね。
調理方法を工夫しよう

料理に何が入っているのかがわかると、子どもは安心して食べられる一方、苦手な食材だと食べないという〝選択〟ができてしまいます。苦手を克服するためには細かくして混ぜる以外にもいくつか方法があるので、子どもに合った調理法を見つけてみましょう。
①食感を変える
同じ食材でも調理法によって「煮るのか、生で食べるのか」で食感は全く違います。例えば、煮た大根が苦手な子の場合、生のままスティック状に切って味噌マヨを添えるだけで食べられるようになることがあります。逆のパターンもありますね。
また、野菜の天ぷらをイメージしてみてください。揚げると苦みや香りが抑えられたり、サクサクとした食感が加わったり、油のうまみで食べやすくなることがあります。揚げ物が苦手という場合には、少ない油でも平らで小さな小判型にすればカリッと揚げやすく、食べるきっかけの一つになるかもしれません。
②見た目、場所を変えてみる
いつも切り身で食べている魚を一尾丸ごと焼いて並べてみることで、食材の本来の姿や小さく切る前の料理の姿を見ることも新鮮な体験です。「魚」に対する子どもたちのイメージが変わると思います。ただし、頭や骨がついていることで抵抗を示す場合もありますので、お子さんの性格などへの配慮は必要です。
型を使って星やハートの形にしてみるのも楽しく、子ども自身が一緒に関われる工夫になります。「盛りつける器をお弁当箱にする」「紙皿を使ってみる」など、通常とは違う器にしてみたり、食べる場所を変えてみたりするなど、「いつも」の食事を少し変えてみるのもいいですね。
まとめ
子どもの偏食は、無理強いするよりも、工夫することで少しずつ克服できることが多いです。
まずは、同じ栄養がとれるほかの食材を取り入れながら、「楽しく食べる」雰囲気を作ること、「長い目で見守ること」、これらを意識しながら、少しずつチャレンジしていきましょう!