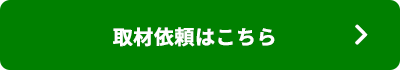ニュートリション関係者の人物背景や取り組みについて紹介する永続企画。第3回目は、帝京大学助教(スポーツ医科学センター所属)で、管理栄養士の藤井瑞恵さんの半生を振り返る。
トレーナー志望からスポーツニュートリショニストへ

小さいころから体を動かすのが好きで、いろいろなスポーツをしてきました。中学時代はバレーボール部、高校時代はテニス部に所属し、青春時代を過ごしました。残念ながらプロやトップレベルを目指すほどの実力ではなかったため、プレーヤーとしては一区切りして、選手をサポートする側に回りたい、スポーツの仕事をしたいと思い、トレーナーの道を志すことにしました。高校卒業後はスポーツが盛んな順天堂大学に進学しました。
ところが、進学した順天堂大学はメディカル分野で有名でしたが、トレーナーを養成する環境はまだ整っていませんでした。大学でスポーツ関連の講義を受けて知識を蓄えていたものの、トレーナーになるために実際にどのように生かせばいいかとか、どういう手順を踏めばいいか、全くわかりませんでした。部活に所属しながら機会を待つといった感じでした。
入部したスキー部では、夏場のオフシーズンに体力づくりをしなくてはいけないんですが、ローラーブレードや夏スキーなど遊ぶことに夢中でした(笑)。順天堂大学では1年生は全寮制で、入寮当時は毎日パーティー(笑)。生活が乱れて体重が急増してしまいました。その後、極端な食事制限をして減量しましたが、リバウンドをしてしまい、うまくいきませんでした。
「このままではマズい」と危機感に迫られて生活を見直した時、「極端な食事制限は続かないし、逆効果、食べながら有酸素運動を増やして少しずつやせるにしたらうまくいくかもしれない」と思って実践してみたんです。すると、効果てきめん、リバウンドせずに、減量もうまくいくようになりました。体を変えるには、食と運動の両方で実践することの大切さを知りました。
それから、食や栄養にも興味を持つようになり、視点も変わって「スポーツや運動と食は関連性がある」と思うようになりました。順天堂大学のスポーツ部活動生やスキー部の人たちはトレーニングを一生懸命やるんですが、食に気を使うことがほとんどなく、食を意識すればもっと良くなるんじゃないかなと考えていました。
ちょうどそのころ、スポーツ現場で栄養指導・サポートをしている管理栄養士の先生の話を聞く機会があり、「食から選手をサポートして行きたい!」と思い、進むべき道を見つけました。このころは少し道に迷っていたので、話を聞くことができて本当に良かったと思います。
順天堂大学を卒業してからはスポーツニュートリショニスト(栄養士)を目指し、管理栄養士の資格を取得するため、スポーツクラブで働きながら専門学校に通いました。このころ、いろいろな方と縁ができて今につながっているので貴重な時間でしたね。
管理栄養士の資格を取った直後は、スポーツ栄養学の勉強会に参加し、東海大学で栄養サポートの現場経験を積ませていただきました。当時サポートしていた女子ラクロス部は月2~3回程度の現場訪問でしたが、ここで経験したことで目標への扉がほんの少し開いた気がしました。
その後、勉強会で知り合った方のご縁でトレーニングと栄養指導ができる人材を求めていた青山学院大学のトレーニング施設で働くことになり、学生、教職員向けに健康のための食事指導、簡単なトレーニング(運動)指導を担当することになりました。
トレーニングと栄養の指導ができる専門家は当時ほとんどいなくて、両方を知っていた私に白羽の矢が立ったわけですが、学生時代にトレーニングの勉強をしたことが無駄になりませんでしたね。
大学からは「チームも見てほしい」という要望もあり、バスケットボール、バレーボール部など部活動の栄養指導をするようになりました。選手の体組成測定の際に同席して体の変動を見たり、トレーナーと連携して選手の体づくりのためのアドバイスをしたりしていました。日常業務をこなしながら、日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士の資格を取得したのはちょうどこのころです。
そして、2016年からは帝京大学に移り、スポーツ医科学センター1)・フィジカルチームの一員としてラグビー部2)を専門的に見ています。やはり、チームに帯同して毎日のように選手と顔を合わせ、接するのは楽しいですし、やりがいもあります。
現在は帝京大学に在籍する栄養チーム(計7名)のリーダーを務めていて、現場の意見を聞いて改善策を見出したり、各チームのリーダーが集まるセンターの運営会議に出席してセンターの方針を決めたり、少し責任を負う役割も増えてきました。8割が現場、2割がマネジメントといった割合で毎日を過ごしています。
1) センター長を頂点に、フィジカル(トレーナー、栄養士)、メディカル、サイエンス、テクノロジーの4チームで構成され、各専門家が科学的にアスリートをサポートする体制が整っている。
2) 全国大学ラグビーフットボール選手権大会で前人未到の9連覇(2009~2017年)を達成した大学ラグビー界の雄。2019年W杯では日本代表31人中7人が帝京大学ラグビー部出身。

名門ラグビー部に帯同、「選手の観察」が目標達成の肝

ラグビーはコンタクトスポーツなので、まずケガをしないための体づくりが大切になってきます。その上で、フォワードならパワー負けしないようにもっと増量しようとか、バックスなら瞬発力を落とさずに筋力アップしようとか、ストレングスコーチなどのスタッフと情報共有しながら選手のパフォーマンスアップを目指します。
例えば、増量を目標にする選手がいたとして、食事の量、内容、サプリメントの活用とトレーニングで強化を図るのですが、食の面で「脂肪がつき過ぎてしまう」、「増量しにくい(体質)」、「食が細い」など、目標達成に向けた課題も見つかってきます。
選手たちの食の課題を見出すためには「よく観察すること」が重要です。私はチームスタッフとして練習や合宿に帯同しているため、練習時はもちろん、食堂へ行って選手たちの食事の仕方や量、顔色をうかがいつつ、会話をしながら選手たちの状態を把握していきます。
毎日バランスのいい食事を摂るというのは前提としてあるものの、やはり個人で体質や習慣が異なってきますので、すべてが思い通りに行くとは限りません。身体強化のための食のアプローチはもちろん大事なのですが、選手たちの体調、体質を把握して良いコンディションを作るために、食事や補食の工夫を施したり、アドバイスをしたりするのが私たちの仕事になってきます。
現在、ラグビー部には約150名の部員が在籍しており、2人で栄養サポートをしており、1年間でみると、春先はチーム全体へのアプローチを中心にしています。
普段の生活では「残食はしない」「規定量の食事を摂る」といった、チームで決めたことを全員が実行していくように、指導・教育していきます。練習時には、リカバリーのためのプロテイン摂取を徹底しています。
ラグビーはエネルギー消費が激しいスポーツなので、練習の合間に小さいおにぎりやバナナなどの補食も欠かせません(練習メニューによって異なる)。エルゴジェニックエイド3)も有効なのですが、まずは、食事から体づくりやコンディションづくりを考えられるように、アドバイスをしています。
3) パフォーマンスアップを目的としたサプリメント。クレアチン、HMB、β-アラニンなどがあるが、各国によって定義はさまざま。

ラグビーシーズンが深まってくる秋までに、こうしたチーム全体の基本方針に沿って、食のアプローチはしていきますが、秋以降はトップチームの選手たちへのサポートに重点を置いていきます。
オフの日の食事管理から、試合後のリカバリーに何を摂っているか、試合で消費した体力(体重)がどれだけ戻っているか、水分補給はきちんとできているかなど、一人一人の細かいコンディションについて数字を用いながら細かくチェックしていきます。コンディションで課題が見つかった選手に対しては、個別に話をしながら次の試合をベストな状態で臨めるように改善を図っていきます。
本当は選手一人一人をしっかり見ていければいいのですが、物理的に難しい部分があります。ですから、チーム全体で決めた最低限のルールを、意志を持って自主的に考えて行動してもらえるように、私たちは最初に指導していきます。
スポーツ現場では「選手を強くする」、「チームが強くなる」ことが目指すところです。栄養の部分は強化のための一過程で、選手たちには「栄養も大事だけど、トレーニングと組み合わせてこそ効果が出てくる」といったことをよく話します。
自身の強化やコンディショニングと栄養の関わりがわかっている選手はどんどん実践していきますが、当然そうでない選手もいて栄養だけの話をすると理解が難しい面もあります。
選手たちの「こうなりたい」という理想像を作り上げるために、指導者や各分野のスタッフ、スポーツニュートリショニストが一緒になって考え、結果に結びつけていく。こういった姿勢がラグビー部には浸透していると思いますので、とてもいい環境で仕事をさせていただいています。
早いものでラグビー部に来て4年になり、培った現場での指導・サポート経験を次の世代に伝達していく立場にもなりつつあります。でも、やはり選手たちが日々成長していく姿を見ていくのはとてもやりがいがあるので、これからもスポーツ現場で栄養の大切さを伝えていければと思っています。
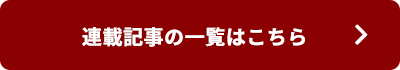
【栄養関係者の皆様へ】
編集部では、企画にご登場いただける関係者を募集しています。
「自己PRとして記事を書いてほしい」「活動を知ってもらいたい」という方は大歓迎です!
お名前、活動内容(簡素で結構です)など、下記よりお気軽にご連絡ください。