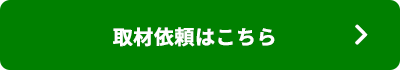ニュートリション関係者の人物背景や取り組みについて紹介する永続企画「ニュートリションな人々」。第2回は、栄養学博士で株式会社ドーム執行役員(サイエンティフィックオフィサー)の青柳清治さんの半生をお送りする。
長い間欧米の企業で要職を務め、現在は日本のスポーツニュートリション分野の発展に力を尽くし、幅広い活動をおこなっている。
“アメリカ人”として青春時代を送り…

青柳さんは1976年、エレトロ二クス関係の販売会社に勤務していた父の転勤でアメリカ合衆国のロサンゼルスに渡った。中学2年生の時だ。当時を振り返り、青柳さんはこう語る。
「あのころは今ほど日本人を受け入れる体制が整っておらず、全く英語が話せなかったし、日本人もほとんどいないので、ずいぶん苦労しました。でも、周囲の人たちに本当に親切にしてもらって、無事に高校を卒業することができたんです。もう日本人というより、アメリカ人として生活を送り、青春時代を過ごしたといっていいでしょうね(笑)」
近年の在米邦人の数は約50万人とされている。1997年に25万人を突破して以降、約20年で倍増しているが、青柳さんが渡米した1976年当時、在米邦人はマイノリティだった。今ほど日本の文化や国民性に寛容ではない時代。言葉ではいえない辛酸も味わったはずだ。その中で、語学習得、勉学に精力を傾けて高校卒業時には成績優秀者として表彰されるまでに至った。
青柳さんは大学を決める際、日本に帰国する考えはなく、アメリカで永住しようと考えていたことから、南カリフォルニア大学(USC)、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)、オクシデンタル大学(Oxy)の3校に進路を絞った。いずれも、アメリカの名門大学で多くの著名人、政治家、研究者などを輩出している。
USCとUCバークレーは比較的大きな規模で学生数も多い一方、Oxyは比較的小規模で特定の分野に偏らずさまざまな分野が学べる、いわゆる「リベラル・アーツ・カレッジ」。一学年も少数でじっくり勉強できる環境だと思い、後者を選択した。2学年上にはバラク・オバマ前大統領がいた。物心つく頃からダーウィンの進化論に共感を覚えていた青柳さんは、大学で生化学を専攻する。
「僕はね、生粋の『ダーウィニアン』。なぜ人間がここまで進化したのかを考えると面白いんですよね。古くから人間が脈々と受け継いできたDNAが進化して、今に至ると思っているんです。生化学を極めれば、その答えに少しでも近づけるのかなと思っているんですよ」
4年間の大学生活でしっかり勉強をした青柳さんは「日本人なのに日本のことを何も知らない」と感じ、日本国内でアミノ酸の研究・開発をおこなう企業で研究者としての職に就いた。
糖を微生物で発酵し、アミノ酸を生産する技術の応用でアルギニンを生成し、アルギニンの生産株からオルニチン、シトルリンを生産する技術を見出した。それが1985年。今でこそ消費者の認知度が高いアルギニン、オルニチン、シトルリンのアミノ酸3種はこの頃から研究が行われ、青柳さんはその黎明期にかかわっていた。
その後、アミノ酸の用途開発の研究に携わることになる中で探求心が強くなり、社内留学制度を利用してイリノイ大学の大学院に進む。ここで、アミノ酸研究の第一人者、デイヴィッド・H・ベイカー博士に師事し、研究スキルを磨いていった。留学期限の2年で、通常は4年かかる博士課程も修了できるメドがついたため、そのままアメリカに残って栄養学博士号を取得した。
博士号を取得後、米国製薬大手「アボット・ラボラトリーズ」に入社。オハイオ州にある研究所で病態別栄養学の研究に従事した。ここではリウマチの栄養治療をテーマに用途開発研究を進め、在籍中には3つの米国特許を取得した。
「リウマチは自己免疫異常が原因で、免疫組織が自分の関節を壊してしまい、痛みが発生するメカニズムになっています。このときⅡ型コラーゲンをごく微量に摂取すると免疫系が変化して自分の抗原を攻撃しなくなり、リウマチが改善されるということを突き止めました。アボット社在籍時にいろいろな研究をさせてもらって、薬ではなく栄養をきちんと摂ることで病気の予防に役立つことがよくわかりました。この時期はとても面白かったですね」
そのほか、栄養摂取による抗炎症作用の研究にも力を注ぎ、EPAが持つ作用に着目。EPAを配合した栄養剤「オキシーパ」の開発に着手した。オキシーパはやけど等でICUに搬送される患者用の栄養剤。長期間ICUに入ることを余儀なくされた患者に飲ませると、EPAの抗炎症作用から早期にICUから離脱できるという臨床効果が得られている。ほかにも、COPD(慢性閉塞性疾患)患者向け、糖尿病患者向けの栄養剤を次々に開発し、病気の予防や治療という観点から栄養摂取の有用性について考えるようになった。
アメリカのノウハウを日本へ導入、世界中を飛び回る日々

青柳さんがアボット社で病態別栄養の研究・商品開発を進めていたころ、日本には栄養剤に配合する良質な原料が数多く開発されていた。
原料探索のため、頻繁に帰国するようになり、臨床栄養の専門家とも交流をもつようになった。専門家らと日米の臨床栄養に関する意見交換などをするうちに、NST(ニュートリションサポートチーム)が日本国内に存在していないことに気づく。
NSTは、患者に最良の栄養療法を提供するため、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師などのスペシャリストで構成され、欧米ではNSTが現場でチーム医療を施すことが当たり前だった。
そこで、青柳さんは日本国内の専門家や関係者に最先端の現場を見学してもらい、日本とアメリカの橋渡しをした。この活動を契機に、日本版NST誕生への流れに変わり、現在ではNSTは医療現場で定着している。
日本へ頻繁に行くことが多かったため、1998年に大日本製薬とアボット社の合弁会社「ダイナボット」(現:アボット・ジャパン)の栄養剤関連の総責任者として赴任。10数年ぶりに日本を中心に活動することになった。ここでも日米の違いを発見することになる。自らの専門分野である病態別栄養の研究が日本では行われていなかったのだ。そこで、米国でおこなっていたビジネスをそのまま日本にも流用することにした。
また、医師の栄養への理解を深めることを目的に、日本静脈経腸栄養学会と合同で、アボット社が開発した臨床栄養教育プログラム「トータルニュートリションセラピー(TNT)」の国内普及プロジェクトにも携わった。TNTは今でも多くの医師が受講しており、NSTにはTNTを受講した医師が1名常勤する必要になっている。
さらに、「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」の確立にも一役買った。身体計測は患者の栄養状態を知るため(栄養アセスメント)に重要な項目だが、当時は欧米人の指標を使って日本人に当てはめていたため、意味をなさないことが多かった。
日本栄養アセスメント研究会と一緒になって、栄養アセスメントキット(皮脂厚や腕の周囲長を測定する道具)を普及させ、さらに年齢、男女別など日本人の体格の基準を事細かく決めていった。
「米国と日本ではやはりいろいろな違いがあって、特に優れたプログラムだったTNTとJARD2001の普及活動は当時力を入れていて、日本の臨床栄養分野の発展に少なからず貢献できたのではないかと思っています。自分でも誇らしい仕事をしたと胸を張れます」
海外の最先端ノウハウを日本へ“輸出”する役目をいったん終え、アメリカに戻った青柳さんは世界を舞台に栄養剤ビジネスを展開する要職に就いた。もちろん、力を注いできたTNTの普及活動を、今度は南米、東南アジアで進めていった。2009年までの7年間世界中を飛び回り、1年間のうち8割は海外出張という多忙な日々が続いた。
2009年からは、アボット社がシンガポールに栄養研究所を設立することになり、現地に赴任。研究者を集めたり、分析機器を取りそろえたり、試作品開発の施設づくりまで、まさしくゼロからのスタートで研究所を立ち上げた。
一定の成果を挙げた後、米国製薬大手「GSKグラクソ・スミスクライン」へ移籍。ヘルス事業部で薬事、品質管理、開発すべての部門を統括する責任者を務めた。歯磨き粉「シュミテクト」、「アクアフレッシュ」、入れ歯洗浄剤「ポリデント」、入れ歯安定剤「ポリグリップ」、総合感冒薬「コンタック」など、日本でもなじみ深い商品の開発に携わった。
ビジネスは順調だったが、ここで自らがライフワークとしていたニュートリションから離れた仕事をする毎日に疑問が生じる。
「ニュートリション分野に戻りたい」-そう思っていた矢先に乳業大手「ダノン」からの誘いを受けて移籍。日本国内でもヨーグルト需要が爆発的に高まっていた2012年のころだ。
研究開発部長を務め、OIKOS(オイコス)、Bio(ビオ)に携わった。そして、2015年1月、スポーツウェアブランド「アンダーアーマー」の日本総代理店である「ドーム」で、サプリメントブランド「DNS」の責任者として辣腕を振るっている。
スポーツニュートリションとの邂逅
臨床栄養分野で長く活躍していた青柳さんがなぜスポーツニュートリション分野に“転身”したのか。話はアボット社在籍時にさかのぼる。
当時アボット社が所有していたニュートリションブランド「EAS」は、「栄養とトレーニングで体の状態を変化させる」という肉体改造プログラム(Body for Life)を展開していた。
スポーツ栄養学と筋トレ、および有酸素運動を融合した3カ月のプログラムで、多くの米国人が肉体改造、ダイエットなどで成果を残していた。青柳さんも肉体改造をするためにプログラムを実行したところ、劇的に変化したことを実感する。
もともと栄養が体に及ぼす影響を専門に研究していたこともあり、体作りとニュートリションの相関と重要性を即座に理解した。トレーニングの知識を独学で学び、パーソナルトレーナーの資格も取得した。
海外でトレーナーの資格を取得する過程で講座を受ける中、半分がニュートリションの話で、トレーニングとニュートリション、スポーツとニュートリションは切っても切り離せない関係であることがわかった。
「僕の専門分野である臨床栄養と、スポーツニュートリションはとても似ています。例えば、スポーツでいえば、選手がパフォーマンスアップのためにトレーニングを積み、プロテインやアミノ酸を摂取して筋力強化、筋肉増量を図る。
一方で、健康に気をつけている人や中高年の方は、フレイルやサルコペニアの予防という観点から毎日の運動に加えて、プロテインやアミノ酸を摂取する。
『筋肉をつけるためのニュートリション』とすれば、競技スポーツも健康も考え方は同じなんですよね。運動をする人が増えている日本でも、食べることが密接な関係を持っていることをもっと知ってほしいですし、その考えは浸透しつつあると思っています」
正しいことをやるーアンチ・ドーピング認証システムの是正
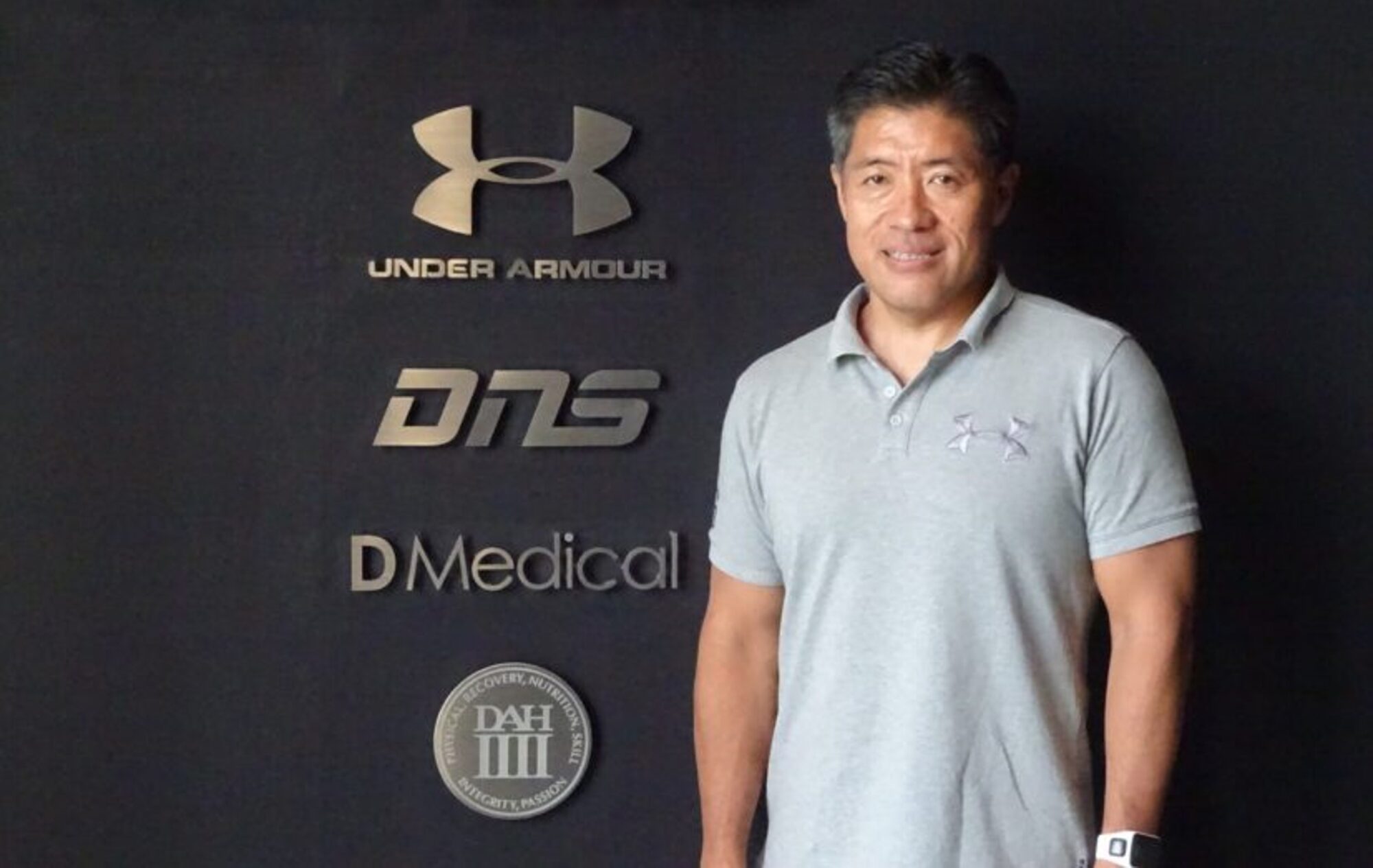
青柳さんを語る上で欠かせないのは、サプリメント製造にかかわるアンチ・ドーピング分析の必要性を食品業界に植えつけたことだ。
東京五輪の開催決定を機に国内でもアンチ・ドーピングの機運が高まり、ドーピングコントロール下にあるスポーツ選手が口にする物の安全性が問われることになった。
スポーツ選手に商品を提供しているサプリメント・食品メーカーは当然、ドーピング物質の有無に関する分析をして安全性を担保したいが、さまざまな理由があって日本では数年前まで、事実上メーカーがドーピング分析を受けることができなかった。
こうした状況が続いていた中、青柳さんは「高度なアンチ・ドーピング分析・認証を日本でも可能にする」「海外の分析力に長けた機関と連携する」「これまでアンチ・ドーピング分析ができなかったメーカーの受け皿を作る」-この3つのミッションを遂行すべく、水面下で動いた。
国際的なアンチ・ドーピング認証「インフォームドチョイス(IC)」を展開している英国の大手分析機関「LGC」と日本での展開について粘り強く交渉し、2016年秋にICは日本に上陸した。
「最初はLGC社に全く相手にされなくて・・・。連絡しても返答がないという時期もありました。それでも、日本国内のアンチ・ドーピングに関する体制の問題や、東京五輪が迫る中で、LGC社が日本でマーケティングを展開する意義などを説いていくうちにこちらの思いをわかってくれて、ようやく前に進むことができました。
このプロジェクトは、メーカーに所属する僕が訴えるのはもちろんですが、健康食品の規格に熟知しているバイオヘルスリサーチリミテッド社・池田秀子さんの協力は欠かせませんでした。池田さんが持つ専門知識や実績がなければ、ICがこれほど日本に受け入れられなかったでしょう。社内でも『正しいことをしよう』『スポーツ界の闇と戦う』という機運がありましたね」
余談ではあるが、スポーツニュートリション分野で人気が高まっているHMB1)を日本に持ち込んだのは青柳さんと池田さんである。
当時、海外でHMB含有の臨床栄養製品を製造・販売していたアボット社は日本での展開を目指していた。その担当者が青柳さんだったのだが、食薬区分2)の関係でHMB含有製品の日本での販売は認められていなかった。
そこで、青柳さんは食品規格の専門家である池田さんに相談し、HMBを日本国内で展開できるように働きかけ、品質や効果・効能に疑いのなかったことがわかり、僅か2年というスピードでHMBが食品・サプリメントで使用できるようになったのだ。
1) 正式名称「βヒドロキシβメチル酪酸」。期待される効果としては、筋肉の合成・筋疲労の軽減などがある。
2) 日本では食品と薬品で使用できる原料が分けられており、HMBは食品やサプリメントに配合できなかったが、2010年に認可された。
ICを展開するLGC社では、商品にドーピング物質が検出されていないことを証明する分析結果をHP上で開示しており、スポーツ選手は一目で安全性を確認できる。また、もし分析の過程でドーピング物質が検出された場合、メーカー側に伝えて迅速に対応できるよう、極めてオープンな体制をとっている。
ドーピング問題には、コンタミネーション(製造過程での異物混入)や配合原料がそもそも禁止物質で気づかずに使用していたなど複雑なので、機会があるときに説明したい。
こうして出会った2人がタッグを組み、アンチ・ドーピング分析・認証を日本でも可能にしたのだ。近年では、LGC社のアンチ・ドーピング分析プログラムを利用するメーカーが急増しており、その数は2020年2月時点で40社を超える。
国内のスタンダードとなりつつある中で、スポーツサプリメントメーカーの大半は利用しているといっていい。また、グローバルな視点から見ても、名だたるブランドがプログラムを利用していることから信頼性・知名度は高い。
「メーカーが商品のアンチ・ドーピング分析を受けるのは当たり前のことだと思いますよ。もし、サプリメントからドーピング物質が検出されたら、スポーツ選手の人生をめちゃくちゃにしてしまいますから。これまでは分析を受けられる機関がなかったので仕方ありませんでしたが、食品業界ではアンチ・ドーピングの意識が変わってきています。
一番大切なのは、使っていただくスポーツ選手や消費者のみなさん。アンチ・ドーピングの考え方や、食品やサプリメントにICの認証マークがついている意味をよく知ってもらわなければなりません。だから、これからもいろいろな場所で多くの方に会って、地道に説明していきます」
スポーツニュートリションを身近な存在に
アンチ・ドーピングに関する食品業界への周知活動は一息つき、青柳さんは使ってもらう側への理解を求めることにシフトチェンジしている。アスリートはもちろん、スポーツ業界の専門家や指導者などにアンチ・ドーピングの重要性を訴えるため、日常業務の合間を縫って活動を続ける。
アンチ・ドーピングの周知活動以上に、青柳さんが今最も力を入れているのが、、管理栄養士、薬剤師、学生、企業人が月1回集まる「すぽべん(スポーツ栄養勉強会)」での活動である。
「すぽべん」では、ニュートリションはもちろんのこと、運動生理学、生化学などスポーツを取り巻く学術に関する議論や発表が定期的に行われ、幅広くさまざまな視点からスポーツや運動を掘り下げているのが特長である。
2017年には「すぽべん」のメンバーが中心となり、海外の最新知見を日本語訳したスポーツ栄養ガイドライン「Nutrition and Athletic Performance」を刊行した。海外の最新情報を日本にも導入し、スポーツニュートリションの発展のために日夜研究が進められている。さらに、翌年には国際スポーツ栄養学会のポジションペーパー「ISSN Position Stand: Protein and Exercise」を和訳して世の中に提供している。また、海外のスポーツニュートリション関係者・研究者が一堂に会する、国際スポーツ栄養学会(issn)東京大会「issn Tokyo」の大会長として、準備に奔走している。
「海外の最新情報を届けることはとても大事なこと。そもそもどこから情報を取っていいのかもわからないし、難しいのではないかと思っています。『すぽべん』では、なかなか知り得ない海外のスポーツニュートリション、その周辺情報も積極的に活用しながら、国内の最新知見を組み立てて、情報を発信していきたいと思っています」
青柳さんのこれまでの活動を振り返り、共通しているのが海外の最先端を日本に導入すること。ある意味、海外と日本に橋を架ける役割を担っていたといえる。
これは、海外生活が単に長かったからではなく、研究者やビジネスマンの視点を持って日本を見つめていたからこそ、足りないもの、取り入れなければならないものがわかったのだろう。
現在、日本のスポーツニュートリション分野は、イノベーションが進んでいる。その中で、深い知識と広い視野を持つ青柳さんの存在は欠かせまい。これからの活動に注目したい。
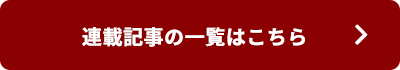
【栄養関係者の皆様へ】
編集部では、企画にご登場いただける関係者を募集しています。
「自己PRとして記事を書いてほしい」「活動を知ってもらいたい」という方は大歓迎です!
お名前、活動内容(簡素で結構です)など、下記よりお気軽にご連絡ください。