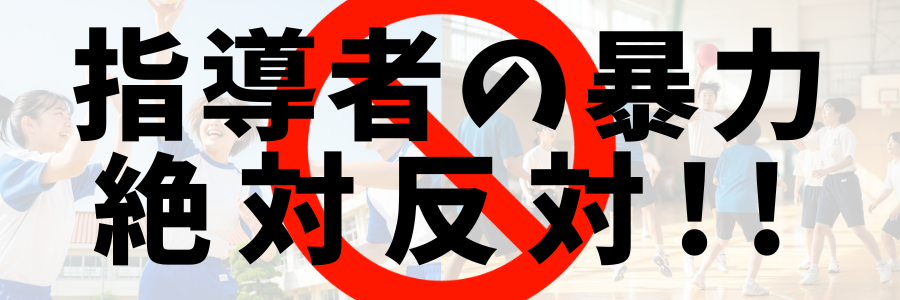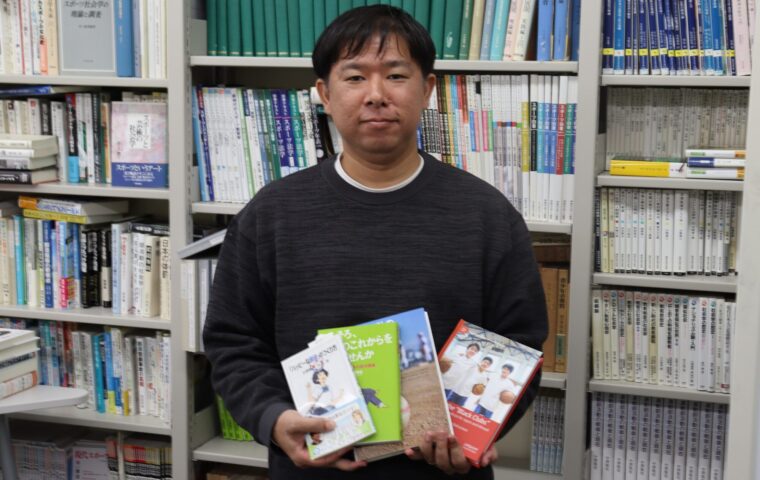なぜ「続ける」ことが難しいのか?
「運動しなきゃと思っても、続かない」「何度やっても三日坊主で終わってしまう」――運動を習慣にしようとして挫折した経験、誰もが一度はあるのではないでしょうか。
多くの人が「自分には意志がない」と自信を失ってしまいがちですが、実は運動が続かないのは性格や根性の問題ではなく、「脳と行動の仕組み」の問題です。
私たちの脳はホメオスタシス(恒常性)という性質が備わっており、変化を避けて今の状態を保とうとする傾向があります。これは、体温や血圧のような生理的な安定だけではなく、行動や心理面にも強く影響します。
新しい運動を始めようとすると、脳はそれを「非日常=ストレス」と捉え、無意識に元の楽な状態に戻ろうとしてします。つまり、続けられないのは「自分がダメだから」ではなく、生物として自然な反応であるといえます。
では、どうすればこの〝脳の抵抗〟を乗り越え、運動を日常の一部に変えていけるのか? 本稿では、行動科学に基づいた習慣化のメカニズムと、実践的な工夫や年代別の継続戦略を基に、誰でも取り入れられる「続ける力」の育て方をご紹介します。
習慣化のカギは「やる気」ではなく「仕組み」
よくある誤解が「やる気が出たら始めよう」という考えです。しかし、脳科学や行動心理学によれば、やる気(モチベーション)は行動を起こした後に湧いてくるものとされています。
例えば、「今日は面倒くさい」と思いながらも、試しに外へ出て散歩を始めてみたら、10分も経たないうちに気分が前向きになり、「歩いて良かった」と感じた経験はないでしょうか。
これは、行動が脳の報酬系を刺激し、気分を高める物質(ドーパミンやエンドルフィンなど)が分泌されることによるものです。つまり、「やる気があるから動く」のではなく、「動くからやる気が湧いてくる」といえます。
このメカニズムを支えるのが、「習慣のループ」と呼ばれる行動の枠組みです。習慣は「きっかけ(Cue)」→「行動(Routine)」→「報酬(Reward)」という3つのステップで形成されるされています(チャールズ・デゥヒッグ「習慣の力」より)。
朝のストレッチルーティーンを例に挙げると、「朝起きたら水を飲む(きっかけ)」→「ストレッチを5分だけ行う(行動)」→「すっきりした気分になる(報酬)」(図1)といった流れを日々繰り返すことで、運動は徐々に「無意識の行動」として定着していきます。

〝小さく始める〟が最大の戦略、抵抗感を減らすことがカギに
運動を習慣化するうえで最も失敗しやすいのが、「最初から完ぺきを目指す」ことです。
毎日1時間のジム通いをしようと決意しても、現実的には多くの人が続きません。むしろ、「1日5分だけ」「階段を使う」「家でラジオ体操をする」など、心理的なハードルが極端に低い行動から始めるほうが継続率は高くなります。
実際、習慣形成に関する研究1)では、新しい習慣が自動化されるまでには平均66日を要し、そのプロセスには個人差が大きいことが示されています。
また、習慣を構築する際にもっとも重要なのは「頻度」と「抵抗感の軽減」であり、「日数のカウント」ではないことも指摘されています2)。
さらに、行動科学者であるB. J. フォッグの「Tiny Habits」理論3)でも、小さな行動(例:歯磨きの後にスクワット1回)を既存の習慣に紐づけることで、無理なく継続できることが明らかにされています。
こうした小さな行動は、「達成感」というポジティブな報酬を生み、行動ループの定着を後押しします。
運動習慣化の第一歩は、「毎日5分だけラジオ体操」「通勤時に1駅だけ歩く」といった、「心理的な負担の少ない行動」を、なるべく高頻度で反復すること。
週に4回以上の頻度が「慣れ」を生みやすいとの報告4)もあり、週2〜3回で挫折しがちな方は、まず回数より「抵抗感を減らす設計」が重要です。「できる自分」を実感できる小さな成功体験こそ、習慣化の原動力になります。
年齢や立場に応じた「運動継続のコツ」 すぐにできる3つの工夫
運動を続けるのは簡単なことではありません。年齢や生活環境によって壁も違いますが、少しの工夫で習慣化はグッと近づきます。今回は、誰でもすぐに試せる3つのポイントをご紹介します。
①小さな成功体験を積み重ねる
「昨日より5分長く歩けた」「スクワットが1回多くできた」など、日々の小さな進歩に目を向けましょう。達成感がモチベーションになり、継続の力になります。
②「ながら運動」で時間を味方に
忙しい大人には「ながら運動」が味方です。通勤時に1駅歩く、テレビのCM中に軽いストレッチをするなど、日常の隙間時間を活用して体を動かしましょう。
③仲間や家族と一緒に楽しむ
運動は一人で続けるより、誰かと一緒に楽しむ方が長続きします。子どもと鬼ごっこをしたり、友人とウォーキングを計画したり。声を掛け合って励まし合うことが、継続への大きな力になります。
続ける人が活用している「外部サポートの工夫」
運動を続けられる人は、自分のまわりに「続けやすい環境づくり」を上手に取り入れています(図2)。
特に、「目に見える形で成果を記録し、それを誰かと共有する」ことは継続の大きな助けになります。記録を見返すことで達成感が湧き、仲間とのやり取りが支えになります。

「調子の波」とうまくつき合う秘訣
誰にでも体調や気分に波があります。やる気が出ない日や体が重く感じる日は自然なこと。そんな時は、「無理をしない自分を認める」ことが大切です。
完ぺきを目指すより、「今日は少し休んで明日に備えよう」と柔軟に考えることが、長く続けるコツです。計画的に「休息日」を設けることで、筋肉や神経の回復だけでなく、心のリフレッシュにもつながり、むしろパフォーマンスの安定を助けます。スケジュールにあえて、「オフの日」を入れてみるのもおすすめです。
続けることは「戦略」だ
運動が続かないのは、意志の弱さではありません。脳の働きや行動の仕組み、生活設計、そして「がんばらずに続けられる仕組みづくり」が整えば、誰でも「続けられる人」になれます。
大切なのは「頑張る」より「やめない工夫」。できなかった日があってもまた戻れる「柔軟さ」を持つことです。連載2回目では〈疲労とフィットネスのバランス〉、3回目は〈負荷と回復〉を学び、今回は〈継続〉のための具体的な工夫を掘り下げました。
これらはすべて、「安全に」「無理なく」「成長を促す」ための土台。続ける力を育てることが、トレーニングそのものの質を高めます。
次回は、オーバーユースと障害予防
夏休み真っ最中の次回は、成長期の子どもに多い「オーバーユース障害(使いすぎによるケガ)」をテーマにお届けします。
部活動や合宿、練習試合で運動量が増えるこの時期。お子さんや選手から「やればやるほど上達するはずなのに、膝や腰が痛む」という声は聞こえてきませんか? これまでの記事を土台に、成長期特有のリスクや防止策、親御さんや指導者ができることなどを科学的かつ実践的に解説します。(前道 俊宏)
【参考文献】
1) Lally, P etal.: How are habits formed: Modelling habit formation in the real world., European Journal of Social Psychology, 40(6) 998-1009 (2009)
2) Gardner B etal: Making health habitual: the psychology of ‘habit-formation’ and general practice., Br J Gen Pract., 62 (605) 664-6 (2012)
3) Fogg, B. J.: Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything., Houghton Mifflin Harcourt (2019)
4) Wood, W & Rünger, D.: The role of habit in everyday life., Annual Review of Psychology, 67, 289-314 (2016)
【前道先生への質問を募集します!】
トレーニングや怪我予防など、読者の皆さんが持つ疑問に前道先生がお答えします。
五輪やトップスポーツ現場での経験を持つ有識者から直接アドバイスいただける機会は少ないので、ドシドシ質問をお寄せください。質問はこちらから。
※返信のために、お名前(ハンドルネームでも可)・連絡先(メールアドレス)が必要になります。
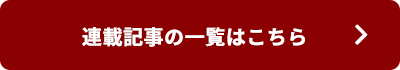

前道俊宏(早稲田大学スポーツ科学学術院講師、東洋大学ライフイノベーション研究所客員研究員)
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)、鍼灸あんまマッサージ指圧師。スポーツ医科学・臨床現場を架橋する研究を推進し、運動器障害の評価と予防、介入効果の可視化に関する研究に従事している。